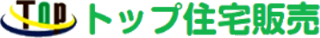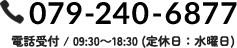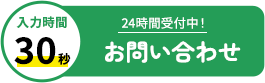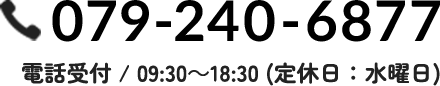お知らせNEWS
築年数が家の売却相場に与える影響は?査定額の仕組みから高く売るコツまで徹底解説2025.05.12

築年数で家の売却相場はどう変わる?戸建て・マンションの傾向

まず、築年数が家の売却相場に具体的にどう影響するのか、基本的な考え方と、戸建て・マンションそれぞれの傾向を見ていきましょう。
築年数と売却価格の関係(基本的な考え方)
家の売却価格は、大きく分けて「土地の価値」と「建物の価値」で構成されます。このうち、築年数の影響を直接的に受けるのは主に「建物の価値」です。
建物は、完成した瞬間から経年劣化が始まり、その価値は徐々に減少していきます。これを減価償却といいます。一般的に、建物の価値は築年数が経過するほど低くなる傾向にあります。
一方で、「土地の価値」は、立地条件(駅からの距離、周辺環境など)や需要によって変動するため、築年数が古くても土地の価値が高ければ、全体の売却価格も高くなる可能性があります。
特に、木造戸建ての場合、税法上の耐用年数(法定耐用年数)である22年を超えると、建物の評価額がゼロに近くなると言われることがありますが、これはあくまで税務上の話です。実際の売却市場では、建物の状態やリフォーム履歴、そして何より土地の価値が総合的に評価されます。
【戸建て】築年数別の売却相場目安
戸建ての売却相場は、構造や立地、メンテナンス状況によって大きく異なりますが、一般的な傾向として、築年数による価格下落は避けられません。
- 築10年程度:新築時の価格から大きく下落することが多い時期です。建物自体の価値もまだ評価されます。
- 築20年程度:木造の場合、建物の評価額はかなり低くなる傾向があります。土地の価格が売却価格の大部分を占めるケースが増えてきます。
- 築20年超:建物の評価はゼロに近くなることもありますが、「古家付き土地」として、土地の価値をメインに取引されることが多くなります。建物の状態が良ければ、プラス評価されることもあります。
あくまで目安ですが、築年数が経過するほど、土地の価値(立地条件など)が売却価格を左右する度合いが強まると考えましょう。
【マンション】築年数別の売却相場目安
マンションの場合、戸建てと比較して価格の下落は緩やかな傾向があります。その理由としては、
- 鉄筋コンクリート(RC)造などが多く、法定耐用年数が長い(例:RC造は47年)
- 立地条件が良い場所に建てられていることが多い
- 管理組合による維持管理が行われている
などが挙げられます。ただし、マンションも築年数と共に価値が下がることに変わりはありません。
- 築10年~15年:価格は下落しますが、まだ比較的人気があります。
- 築20年~25年:下落率は緩やかになりますが、管理状況や修繕積立金の状況がより重視されるようになります。
- 築30年超:大規模修繕の実施状況や、今後の修繕計画、耐震性などが価格に大きく影響します。
マンションの場合は、築年数に加えて「管理状況」が非常に重要な評価ポイントとなります。
土地と建物の価値は別々に考えよう
繰り返しになりますが、家の売却価格は「土地価格+建物価格」です。築年数が古い家の売却を考える際は、特にこの点を意識することが重要です。
建物自体の価値が低くても、土地に十分な価値があれば、高値での売却も不可能ではありません。自分の家があるエリアの土地相場を把握しておくことも大切です。
不動産会社はどう査定する?築年数が査定額に与える影響

不動産会社が家の価値を評価する「査定」。ここでは、査定の仕組みと、築年数がどのように評価に影響するのかを解説します。
不動産査定の基本的な仕組み(3つの評価方法)
不動産査定には、主に以下の3つの方法があります。
- 取引事例比較法:周辺の類似物件(広さ、間取り、築年数などが近い物件)の成約価格や売出価格を参考に、対象物件の個別要因(日当たり、眺望、角部屋など)を考慮して価格を算出する方法。居住用不動産の査定で最も重視されます。
- 原価法:対象物件を現時点で再建築した場合にかかる費用(再調達原価)を算出し、そこから築年数に応じた価値の減少分(減価償却)を差し引いて価格を算出する方法。主に建物の評価で用いられます。
- 収益還元法:対象物件が将来生み出すと予想される収益(家賃収入など)を基に価格を算出する方法。主に投資用不動産の査定で用いられます。
居住用の戸建てやマンションの査定では、「取引事例比較法」をメインとし、「原価法」で建物の価値を補足的に評価するのが一般的です。
築年数が査定額に影響を与える具体的なポイント
査定において、築年数は以下の点で影響を与えます。
- 建物評価(原価法と減価償却):原価法では、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)に応じた法定耐用年数に基づき、築年数が経過するほど建物の評価額が低くなります。
- 市場での需要(取引事例比較法):一般的に、買主は築年数が新しい物件を好む傾向があります。そのため、取引事例比較法で類似物件を探す際、築年数が古い物件は比較対象となる事例が限られたり、価格調整が必要になったりすることがあります。
- メンテナンス状況やリフォーム履歴:ただし、築年数が古くても、適切なメンテナンス(外壁塗装、屋根の修繕など)や、時代に合わせたリフォーム(水回りの交換など)が行われていれば、プラス評価につながる可能性があります。査定時には、これらの情報をしっかり伝えましょう。
法定耐用年数 ≠ 実際の建物の寿命(経済的耐用年数)
よく聞く「法定耐用年数」(例:木造22年、RC造47年)は、税金の計算などで使われる年数であり、建物が実際に住める寿命(経済的耐用年数)とは異なります。
適切にメンテナンスされていれば、法定耐用年数を過ぎた建物でも十分に快適に住めますし、市場価値も残っています。査定においても、単に築年数だけで判断されるのではなく、建物の実際の状態(劣化具合、修繕履歴など)が重視されることを覚えておきましょう。
築20年超えでも諦めない!古い家を少しでも高く売るための戦略

「築20年を超えた古い家だから、高く売るのは難しい…」と考えるのはまだ早いです。ここでは、少しでも有利に売却を進めるための戦略をご紹介します。
まずは現状把握!複数の不動産会社に査定を依頼する
売却活動を始める前に、必ず複数の不動産会社(最低3社)に査定を依頼しましょう。1社だけの査定では、その価格が適正かどうか判断できません。
複数社の査定額や、査定の根拠、販売戦略などを比較検討することで、
- 自宅の適正な相場を把握できる
- 各社の強みや特徴がわかる
- 信頼できる担当者を見つけやすくなる
といったメリットがあります。最近では、インターネットで簡単に複数の会社に一括で査定依頼できる「不動産一括査定サイト」も便利です。
リフォーム・リノベーションはすべき?判断基準と注意点
古い家を売る際に悩むのが「リフォームすべきか?」という点です。結論から言うと、費用対効果(かけた費用以上に売却価格が上がるか)を慎重に検討する必要があります。
- 売却のためのリフォーム:全面的に行うのではなく、買主の印象を左右しやすい水回り(キッチン、浴室、トイレ)や、壁紙の張り替え、ハウスクリーニングなど、ポイントを絞って行うのが効果的です。
- 過度なリフォームは避ける:買主によっては、自分の好みに合わせてリフォームしたいと考えている場合もあります。多額の費用をかけてリフォームしても、それが買主の好みに合わなければ、費用を回収できない可能性もあります。
- ホームインスペクション(住宅診断)の活用:専門家による建物の状態チェックを受けるのも有効です。修繕が必要な箇所を把握でき、買主に対して建物の状態を客観的に示すことができるため、安心感を与えられます。
リフォーム費用と売却価格の上昇分を天秤にかけ、不動産会社とも相談しながら判断しましょう。
「ホームステージング」で印象アップを狙う
ホームステージングとは、売却する物件に家具や照明、小物などを配置して、魅力的に演出する手法です。特に空き家の場合、生活感がなく殺風景に見えがちですが、ホームステージングを行うことで、
- 購入後の生活をイメージしやすくなる
- 部屋が広く、明るく見える
- 物件の魅力が伝わりやすくなる
といった効果があり、内覧時の印象が格段に向上します。不動産会社によっては、ホームステージングのサービスを提供している場合もあります。
「古家付き土地」として売却する選択肢
建物の劣化が進んでおり、リフォームにも費用がかかる場合、あえて「古家付き土地」として売り出す戦略も有効です。これは、建物の価値をほぼゼロとみなし、主に土地の価値で売却する方法です。
買主は、購入後に建物を解体して新築したり、リノベーションしたりすることを前提としています。この場合、土地の広さ、形状、立地条件といった点がアピールポイントになります。解体費用を売主負担にするか、買主負担にするかなど、条件交渉が必要になります。
ターゲット買主層を意識した販売活動
築古物件を求める買主層は、新築や築浅物件を求める層とは異なる場合があります。
○自分でリフォームやDIYを楽しみたい層
○建物の価値よりも土地の立地や価格を重視する層
○投資目的で安く購入して賃貸に出したい層
など、ターゲット層を想定し、その層に響くような物件のアピール(例:「リノベーションベースとして最適」「〇〇駅徒歩圏の希少な土地」など)をすることが重要です。
【戸建て・マンション別】築年数を踏まえた売却手続きの流れと注意点
家の売却プロセス自体は、戸建てでもマンションでも大きくは変わりませんが、築年数が古い物件特有の注意点があります。
家の売却プロセス(共通の基本的な流れ)
- 査定依頼・相場調査:複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を把握。
- 媒介契約:売却を依頼する不動産会社と契約を結ぶ(専属専任、専任、一般の3種類)。
- 販売活動:不動産会社が広告掲載、ポータルサイト登録などで買主を探す。
- 内覧対応:購入希望者が見学に来るため、室内を綺麗にして対応。
- 購入申込・交渉:購入希望者から申込があれば、価格や引き渡し条件などを交渉。
- 売買契約:条件が合意に至れば、買主と売買契約を締結。手付金を受け取る。
- 決済・引き渡し:残代金を受け取り、物件の鍵や関連書類を買主に渡して完了。
戸建て売却特有の注意点(築年数考慮)
- 境界線の確認:古い戸建てでは、隣地との境界が曖昧な場合があります。事前に測量図などで境界を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
- 再建築不可物件でないか:建築基準法や都市計画法の制限により、現行の基準では同じ規模の建物を建てられない(再建築不可)場合があります。売却前に役所などで確認が必要です。
- 雨漏り・シロアリ・建物の傾き:築古物件では発生リスクが高まります。事前にホームインスペクションでチェックしたり、もし問題があれば正直に買主に告知(告知義務)したりすることが重要です。隠していると後々契約不適合責任を問われる可能性があります。
- 設備の状況:給湯器や配管などの古い設備は、不具合がないか確認し、現状を買主に説明する必要があります。
マンション売却特有の注意点(築年数考慮)
- 管理状況・修繕積立金の確認:買主は、マンション全体の維持管理状態を非常に気にします。「管理規約」「長期修繕計画」「修繕積立金の総額や滞納状況」などの書類を準備し、説明できるようにしておきましょう。
- 大規模修繕工事の履歴と予定:これまでどのような大規模修繕が行われたか、今後予定されているか、一時金の徴収予定はないかなども重要な情報です。
- 専有部分と共用部分の確認:リフォーム履歴などを伝える際、どこが自分の所有範囲(専有部分)で、どこがマンション全体のもの(共用部分)なのかを明確にしておく必要があります。
- 耐震基準:1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認であれば新耐震基準ですが、それ以前の場合は旧耐震基準となります。耐震診断の有無や結果も確認しておきましょう。
築年数が古い場合の必要書類や告知事項
築年数が古い場合、上記以外にもアスベスト調査報告書(必要な場合)や、耐震基準適合証明書(取得できれば売却に有利になることも)、過去の増改築や修繕の履歴などが求められることがあります。また、物件内で事件や事故があった場合は、告知義務がありますので、必ず不動産会社に伝えましょう。
まとめ:築年数を理解し、最適な売却戦略を立てよう
今回は、家の売却における築年数と相場の関係、査定の仕組み、そして築古物件を少しでも高く売るための戦略について解説しました。
- 築年数は売却価格に影響するが、それが全てではない。土地の価値やメンテナンス状況も重要。
- 不動産査定では、取引事例や建物の状態が総合的に評価される。
- 複数社への査定依頼、効果的なリフォームやホームステージング、古家付き土地としての売却など、戦略次第で有利に進められる。
- 戸建て・マンションそれぞれの注意点を把握し、信頼できる不動産会社を選ぶことが成功のカギ。
築年数が古いというだけで、売却を諦める必要はありません。この記事でご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に合った最適な売却戦略を立て、準備を進めていきましょう。
最初のステップとして、あなたの家が今いくらで売れるのか、信頼できる複数の不動産会社に査定を依頼してみることをお勧めします。
戸建て売却のご相談ならトップ住宅販売へ
姫路市や加古川市で戸建て住宅の売却でお悩みなら、地域で35年以上の実績を誇るトップ住宅販売にご相談ください。当社は大手のように査定価格が不自然に高くなることはなく、代表自らが対応してムラのない適正査定を行い、市場価格に近い売却価格をご提示いたします。
高すぎる査定であとから値下げを余儀なくされるケースも多いなか、当社では過去の豊富な売却データと地域密着の経験をもとに、誤差の少ない査定価格を算出。離婚や転勤などのトラブル時にも迅速に対応し、スムーズな売却へと導きます。
姫路市や加古川市で戸建売却を考えていて、「本当に売れる価格」が知りたい方、安心して売却をお任せしたい方は、ぜひ一度「トップ住宅販売」へお問い合わせください。
>>お問い合わせ | 不動産の売却/買取/購入/賃貸のお悩みはトップ住宅販売で解決|姫路市・加古川市